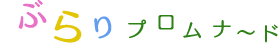2011年08月30日(火) 美術品こぼれ話
絵の木枠のはなし(その1)
収蔵品展「彼方からの光」が始まりました。その出展作品をもとに、「こぼれ話」をいくつかお話しましょう。テーマは木枠についてです。皆様がめったにお目にすることはない、絵の裏側の話です。
これは、今井俊満《東方の光》の展示作業の様子です。横幅6メートルもある大作ですので、展示するにも大人8人がかりです(写真には写っていませんが、裏側に3人います)。
ところで、この作品の画面を後ろから支えている木枠ですが、この大きさを考えるととても単純で、簡素なものです。実際、この状態で作品を持ち上げると、木枠の強度が足りないために画面がたわんだり、反ったりしてしまいます。
では、最初からもっと頑丈な木枠にすればいいじゃないかと思いますが、そうするとものすごく重たくなります。重たくなると、作品を運んだり、飾ったりするのが、よりいっそうたいへんになってしまいます。
そこで作家は、ぎりぎりの強度で、かつ取り扱いやすい木枠を考えます。画家は絵を描く前に、まずはどういう木枠で、どういうカンバスを使うのかなど、とても悩みます。絵の具を塗る前から、作品制作は始まっているのです。
もともと、この作品は、1970年の大阪万博のさい、富士グループ館のVIP室に設置された作品です。部屋の壁に貼り付けてしまうことを最初から想定していたとすると、かりに木枠が強くなくても、壁への取り付け金具で全体をしっかり保持できると計算していたのかもしれません。
万博終了後、パヴィリオンは解体され、この作品も取り外されました。本来の居場所を失い、言わば流浪の旅に出たわけですが、輸送、保管と繰り返される中で、木枠にはかなりの負担がかかったことでしょう。ところどころに補強した跡も見られます。それでもなんとか持ちこたえて、画面を守り続けました。そう考えると、この木枠も健気だなと思えてきます。
3年前、この作品は現在の所有者のご厚意で、当館に寄託されました。木枠は、この作品の誕生と経歴を物語っているようです。